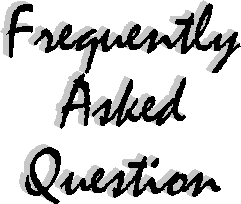
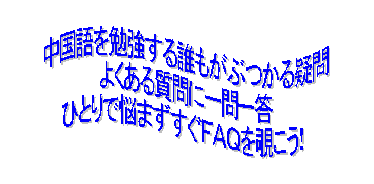
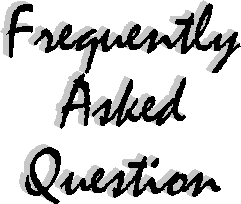 |
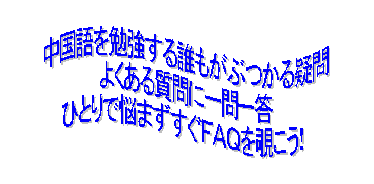 |
![]()
きみはなにをたずねたいのかな?
発音編
engの発音がわからない/そり舌音(捲舌音)がうまくでない/二声と三声の区別が苦手/er化って?
文法編
‘了’の使い方がわからない/可能の表現が区別できない/疑問文と答えかたが混乱してる
その他
辞書はいつから必要なの?/自分で復習できるように参考書はないの?/しゃべれるようになるの?
発音編
A:このサーバーは音声ファイルによく負けるので、当面実際の発音をページ上に乗せることができない点を了解してください(今後改良されたら実現するでしょう)。さて、engという鼻音を伴う母音ですが、実は発音も一通りではないようです。実際に中国で発音されているのを注意深く聞きますと、eの音が微妙に揺れているのが分かります。もし機会があったら中国人の先生に“能”“冷”“城里”“成都”“成功”などを発音してもらうといいのですが、オとエ、それにeを単独で発音する際のいわゆる曖昧母音のいずれかに近く発音されているはずです。アに近いのはよくない発音です。いずれにしてもこれだけ、という風には残念ながらならないので、ケースバイケースで憶えるしかないでしょう。ピンインというのは非常におおざっぱな最大公約数の記号と思ったほうがよいかもしれませんが、そういうことが自分で分かる頃には、こんな質問は卒業ですね。
A:中国語の発音でいちばん難しいのが、この子音かもしれませんね。ちょっとしたコツの問題なので、できる人はとやかくいわずともスッとできてしまうし、ひっかかる人は説明に沢山の言葉を費やしても、なかなかコツがつかめないものです。まず、人間の声というのはどのようにして出てくるのか考えてみましょう。お腹か胸か、どこでもいいですが、声のもとになる息が出てきますね。それが喉のところで声帯を振動させると、ここで母音はどうにか出ますね。でも子音まで出そうとなると、今度は舌が重要な働きをするのです。カキクケコでもナニヌネノでも、舌を宙ぶらりんにしたままでは出ないでしょう?私たちは母語である日本語を発音する際には、そんなことを意識しながら発音しているわけではないですが、私たちにとって外国語である中国語は、独自の音韻体系からなっているので、そこを少し意識的にやらなければならないのです。まず舌の先で、口の中がどういう様子になっているか、よく探ってみましょう。ある音が出るとき、舌が、歯が、どういう位置にきているかについて、自覚的になることが必要です。そり舌音(捲舌音)は一種の摩擦音といってよいのですが、ではいったいどことどこが摩擦し合うのでしょうか?厳密には舌の先とそこを通過する空気というべきでしょう。いちばん大事なのは、空気を通過させるときに、舌の左右両端は口腔内の上の部分(口蓋といいます。歯の裏の土手が終わると、ドーム状に丸くなってますね)から絶対に離さないということ。それに、舌全体を少し奥(喉のほうへ)へ引っ張り戻すことです。この二点を同時に実現するには、舌の中央に少し力を入れて、くぼみを作ってやるのです。これはどちらが先というわけでもなく、舌に空気の通り道を作ってやり、しかも舌の両端が口蓋から離れていなければ、舌の中央は自然と窪んでいるものなのです。舌の先は歯茎の裏の土手の角、と銘記してください。舌の先がそこから少しでも前に出ると、つまりちょうど歯の付け根にくっつくと、空気に押されて舌が口蓋から離れてしまいます。そうなったときの音は、決まって“ツィー”になっています。さて、ここでまだうまくいかないひとは、思い切って舌を丸めて口蓋のドームの一番高い中心部にまで持っていきましょう。そしてそこでチー、シーと発音しましょう。このとき妙な摩擦音が出ていたら、もうしめたものです。その際の空気と舌の摩擦のフィーリングを忘れないようにしてください。前にもいったように、舌の先はちょうど歯茎の裏の土手の角が望ましいので、摩擦の感覚が分かったら、だんだんと舌の先を前に出して、あまりくぐもった音にならないようにしないと、センテンスの中で発音する際に辛くなってしまいますよ。さぁ、何度も練習して、だいたいいいかな、と思ったら、先生のところへ行って聞いてもらいましょう。
A:中国語で“こんにちは”は何といいますか?そう、“ニーハオ”です。ここでは簡体字でもピンインでもなく、カタカナで書きました。日本人にも馴染みのある中国語として、カタカナで書かれることも多いですよね。さぁ、声調とか、正式な発音とか、そういうことはひとまず忘れて、このカタカナを読んでください。たいていは二声+三声ができてますよ。そう、“ニー”が二声(変調した結果)、“ハオ”が三声です。これができて、ほかの場合ができない、というのは、ほとんどの場合が単なる練習不足です。それから、三声をやや低いところから始めて、もっと低くして、それからやや高いところまで持っていく、と理解しているひとも、二声と三声の区別に神経質になりがちです。日常長いセンテンスの間に散在して話される三声は、いわゆる半三声というので、そういった教科書でよく見る座標に描かれたような微妙な曲線を描かないのです。三声ときたら、とにかく低く押さえつけることを考えるべきです。中国人が発音の手本を示す際に、三声の音節を一個だけ取り出して発音を強調する、そんなときには、例の曲線を描くのでしょう。いうまでもなく、そんなことは私たちには不必要です。二声を単独で発音するのも苦手なひと、例えばaという母音を二声で発音してみるなら、まずこれを“ア・ア”と二音節に分けて発音してみましょう。最初のアがドだとしたら、次のアはソだという具合で。もちろん中国語は単音節言語だから、このままではだめです。ドソという音階をクレッシェンドで、つまりつなげて発音できれば、さぁ、それが二声です。そんなに難しくないでしょう?
A: er化というのは、音節の後ろが変化する一種の音便現象です。これは北方の中国語音の特徴で、北京の発音などに顕著です。私たちの学んでいる中国語はいわゆる普通話という共通語で、これは北方音を基礎にしてはいますが、完全にイコールではありません。er化は、ある意味では「なまり」ですから、結論をいえば、気にすることはありません。習得する必要はないでしょう。中国人でも、南方の人間はまったくer化とは無縁の言語生活を送っているのです。外国人が真似するようなものではありません。ただし、普通話の中にも浸透してきたer化については、一通り知っておいていいかもしれません。例えば、“遊ぶ”という動詞“玩wan”を“玩儿wanr”といったり、副詞“漸漸儿jianjianr”(しだいに)“好好儿haohaor”(しっかりと、ちゃんと)といったりするのは、普通話としてよく使われます。上の例はer化に際して発音に注意すべき点を含んでいます。nやngという鼻音の後ろがer化する際、鼻音はほとんど飛んでしまって、直接その前の主母音が巻き舌のようなer化の音便となることです。まぁ、ンといいながら巻き舌にするのは至難の業ですが。それからianという母音がer化したとき、主母音aがer化するわけですが、この場合aは本来の単母音の音に復帰します。こういったことが面倒くさいのであれば、 er化は一貫して拒否すればよいのですよ。
文法編
A:こういう場合には“了”がつき、こういう場合にはないほうがよい、という感覚を自然に身につけるというのは、外国語として、しかも大学に入ってから中国語の勉強を始めたものには、ほとんど不可能ではないかと思います。そこで、一種の規則として括り出せる範囲に限定して、しっかり押さえる、というのがよいでしょう。その前提として理解しておきたいのが、“了”というと私たちはどうしても完了とか終了を連想するのですが、それはどうも誤解だ、ということです。以下では例文を多く掲げる必要上、暫時JIS表示で中国語を表記して、簡体字は用いませんので、その点承知してください。まず“他十八歳了。”という文はどう訳しますか。“彼は十八歳になった”でしょうか?これは“彼は十八歳だ”という現在の関心を表現したものです。過去からついつい今しがたまでの間に、誕生日を経過して、その結果現在彼は十七歳から十八歳への変化を完了した状態を継続している、という意識です。中国語の挨拶言葉でよく使われるのが“我走了。”とか“我先走了。”といった表現です。これは“失礼します”“お先に失礼します”という意味で、相手の前から立ち去る時にいう表現です。これなどは、どうも変化の発生を先取りしているので、上の誕生日の例とも違いますが、少なくとも“私は歩いた”“私が先に歩いた”といった、完了の意味でないことは明白です。ここで整理すると、文末についた“了”は、変化発生以降の現状の確認、という語気を表わし、日本語としては現在形が馴染み易い、ということです。文末の“了”はむしろ、文末の語気助詞に分類されるものです。しかし、“我吃了非常豪華的晩餐。”といった表現もありますね。これは“吃”という動詞の後にくっついている例です。これはもう一つのパターンです。一般に動詞の後ろにつく助詞は動態助詞(時態助詞、様態助詞とも)といって、あまり厳格ではないですが、一応テンス(時制)に関わるものです。私たちが普通連想する完了の“了”はこちらのほうです。完了の意味をはっきり出したい場合は動詞の後ろにすぐ“了”を置くことです。それをいっそうはっきり打ち出したい場合には“我吃了非常豪華的晩餐了。”といった風に文末の“了”と一緒に用います。この場合、現在晩餐が進行中という語気はふつうありません。やっかいなのは、この例のようにSVOの形で、目的語が修飾語などを伴わない単純な形の場合です。“我吃飯了。”というような例です。これはちょっと形からだけでは判断できないのです。動詞の後ろにはないし、文末にあるのだから、第一の例ではないか、というかもしれません。形の上ではそうですが、実際にこれは第二の例として使われることが多いのですね。一般にこれは“我吃了飯了。”の前の“了”が省略された形と説明されるようです。目的語が単純な場合でも、“我吃了飯。”という表現は可能ですが、これは最後に疑問助詞を伴うことはないようです。“了”には文末の語気助詞と、動態助詞の二種類があって、前者は日本語では現在形で訳すのが適当な語気を表わす、後者が完了だと、ひとまず形式的に総括しておくのがよいでしょう。
A:可能の意味を表現するには、助動詞を使う方法と、可能補語を使う方法があります。後者は補語自体が意味を限定することが多いので(つまり、どういうできかたか)、あまり問題にならないと思われます。質問は助動詞三種類の使い分けだと思います。可能の意味を表わす助動詞としては“能・会・可以”がありますが、これは消去法で考えましょう。使い方がかなり限定されているのが、“会”“可以”の二種類です。“会”は練習や訓練を通じて後天的に身についた技能、能力について用いられます。“我会開汽車。”とか“他会説英語。”といった風に使います。これは三点例外的な使い方があります。第一に、言語関係については動詞を省略できるということ。上の例でいえば“他会英語。”でも同じ意味です。第二に、特に練習や訓練を必要としない動詞に用いられる場合で、“他会説話。”“他会買東西。”などという例で、これらは“彼は話上手だ”“彼は買い物上手だ”といった意味。その動作を“上手に行う”という意味が生まれます。否定形では“下手だ”という意味になります。第三は、可能性の有無を表現する場合があるということです。“将来会発生特別困難的問題。”(将来特に困難な問題が生ずるかもしれない)といった例ですが、これは中級レベルですね。今はよいでしょう。次に“可以”ですが、日本語で“できる”と訳せる場合にも、確かに用いられます。しかし、それらは同時に“かまわない”“さしつかえない”といういいかたにも置き換えられるでしょう。つまり、困難や支障がなくて“できる”というのが“可以”です。そして、それ以外は“能”になります。消去法というのはそういう意味です。一般に能力を有している、というような説明がなされることがありますが、適用の範囲は確かに広いので、一般的な定義を与えるのは難しいでしょう。否定形“不能”は単なる“能”の否定形、という場合と、“可以”の否定形として、禁止を表わすことがあります。これは、主観的な印象ですが、私たちが日本語で“できる”という場合を、中国語に置き換えると、五割が“能”、三割が“会”、二割が“可以”といった割合になっているでしょうか。
A:日本語では“これは美味しいですか?”“あなたは学生ですか?”“彼は食べますか?”といった質問にどう答えるでしょうか?一番簡潔な答えかたとしては“はい”“いいえ”で済むでしょう。こういった便利(?)な言葉は中国語には残念ながらありません。中国語の疑問文というのは、大きく分類すると①疑問助詞を文末につけるもの②反復疑問文(大きくいえば選択疑問文)③疑問詞を使ったもの、という三種類になります。①の代表的なものが“ma”(分かりますね。これはちょいとJIS水準にはない漢字)をつけるもの。述語が名詞、形容詞、動詞、いずれでも、答えかたは、述語を肯定/否定して答えます。否定する際は“不”だけでもよい。②は“ma”はつけない。答えかたは①に同じ。③は、そもそも質問する部分、つまり答えを期待する部分を疑問詞に置き換えた構造になっているので、答えかたはそこに答えを入れて、もう一度復誦することになります。よくある間違いは②③の形の疑問文の末尾に“ma”をつけてしまうものです。“ma”というのは疑問符のような疑問文であることを示す標識ではなくて、単に疑問文のある一種類をつくる言葉に過ぎません。疑問文であるから全てくっつけるというものではないのです。ついでにいいますが、疑問文は漢字表記、ピンイン表記を問わず、最後には必ず“?”をつけること。こういう符号類というのも正式な中国語表記の一部分を構成しているからです。
その他
A:いつから、という明確な答えはありません。初級の教科書に載っていることだけをマスターするというのであれば、極端な話、なくともやっていけるような教科書がほとんどだと思います。勉強の進みかたは、先生によって様々でしょうから、実際にはその進度に合わせて、いつ、ということが問題になるはずです。まぁ、ピンインの規則を発音練習とともに勉強している5月くらいまでの段階では、辞書はあまり使いみちもないかもしれません。発音の基礎を勉強しながら、自分の中国語への取り組みかたについて展望ができたなら、そろそろ辞書選びを意識し始めるというところでしょうか。冬学期が始まったときに持っていないのは論外です。次の回答にもあるように、中国語の辞書には、単に字引という以上の役割があるので、勉強が文法事項を中心とする冬学期にはぜひとも机上に置くようにしましょう。
A:中国語には英文法から連想されるような、スタンダードになる規範的なスクールグラマーがないといってよいと思います。そこで、参考書というには少し感じが違いますが、二つの方法があると思います。一つは非常に詳しい教科書をもう一種類参照すること。世の中には、それこそこれ以上の簡潔さはないといった素っ気無い教科書から、鬱陶しいほど説明の懇切な教科書まで、本当にたくさんの教科書があります。もう一つは、例文の豊富な辞書を文法説明のインデックスとして活用することです。みなさんが学校の予習復習に用いる辞書としては推薦できないので、最初に買う辞書にしてはいけませんが、文法確認用に使う参考書としては倉石武四郎『中国語辞典』は簡潔にして要を得た説明が載っていると思います。中国語参考書指南のページも併せてご覧ください。
A:この質問に一般論で答えるのは簡単なようで、実は結構難しいです。そこで、ここはポコペン坂井が責任をもって実名でお答えするのであった。「週二日の授業に漫然と出ているだけでは絶対に無理!第二外国語で中国語を履修した一橋生が、なんとか話せるようになるまで、どんな努力が必要か(やろうと思えばできる程度の)、私の考える所を以下に紹介するのである。一年生のときは、もちろん授業に欠かさず出ること。最低復習は欠かさず、建設的な質問はうるさく教師にぶつける。先生はどーしていつも不機嫌なんですかぁ?とか、そーゆーつまらない質問をしては決していけない。教科書にテープがあったら、入手して一日に三回は必ず耳を通す。すべて必ず口真似をするのである。日常会話に不自由しない程度の文法はすべて(これが重要)初級の教科書にある。だから、一年生のときは、発音の基礎と文法をみっちりやる。それ以外のことには気を散らしても効果はない。休暇中というのがネックだが、一年の夏休みはラジオ講座を聴く。テレビもよろしい。両方ならもっとよい。冬休みは辞書の引きかたに習熟する。材料は教科書のような教材でなく、中国の普通の新聞雑誌の短い文章がよい。最初はいくらも読めないが、ここらが辛抱のしどころ。冬休みに読む材料をください、なんていう感動的な要求が出たら、私はその場で歓喜の余りに思わず熱烈な抱擁と接吻を……そんなことはどうでもよい。こういう努力のできた人は第二年目には語学研修で中国に行くことも考慮する。一年生最後の春休みに上海に行く、もしくは二年生の夏休みに北京に行く、どちらでもよいのである。二年生になったら、時間の許す限り色んな授業(もちろん中国語)に出る。二つは必ずネイティヴの先生の会話を取る。一方、自習として、とにかく中国語の原文を読んで、表現の幅を広げる。授業をこなすだけでは、やはり不足。語彙は辞書を引き引き身につけたものでないと、自分の口からはでてこないし、聴いても分からない。そんな調子で二年の冬学期まで持続できたら、そこで相談にきなさぁい。以上。」と、坂井はいいました。そこで質問ですが、先生はしゃべれるんですかぁ?ポコペン坂井はニッコリ微笑んで、あくまで軽やかなステップを踏んで去っていくのであった。
このページは教室でよく受ける質問や、メイルでくれた質問をどんどん反映させて更新していきます。積極的な参加を期待します!